はじめに
息子が2歳のとき、医師から「自閉症スペクトラム障害」と診断されました。
それは疑いではなく、明確な診断でした。
療育手帳も取得し、特別児童扶養手当も受給していました。
検査ではIQが低く出て、手帳が通るレベルだったんです。
でも実際には、息子は知的障害があるわけではありませんでした。
彼の能力は、そのときの環境によって大きく左右される。
そういう特性を持っていたのです。
診断名がなくなった今
息子はいま、中学2年生。私立中学に通っています。
主治医からはこう言われました。
「もう自閉症の診断名は外していいかもしれない」
「定期診察も、終わりで大丈夫。何かあれば予約を入れて」
つまり、医療の場ではもう“診断名が必要な状態ではない”と判断されたということ。
これを聞いたとき、涙が出そうになりました。
けれど、それと同時に不安にもなりました。
なぜなら……
診断名が消えても、特性が消えたわけじゃないからです。
息子には今も、発達特性があります。
でも、支援や環境調整で十分対応可能な範囲になってきました。
そして、何よりも 彼自身が、苦手を乗り越えて対処できる力をつけてきたのです。
学校に出した診断書から「自閉症」の文字は消えていた
確かに、自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)と診断された当時に比べると、困りごとは激減しました。
当時の息子は、毎日泣き叫び、自傷を繰り返していました。
今の息子は、私立中学からの遅い帰宅時間に疲れていることはありますが、癇癪や自傷はなく、今の生活に適応しています。
入学した時に、学校へは診断書を提出しました。
でも、そこには「自閉症」や「アスペルガー」の文字はありませんでした。
代わりに書かれていたのは、
発達性協調運動障害(=身体の使い方が不器用)
「体育や書字で困難があることがある」
「怠けているわけではなく、特性によるもの」
…という、具体的な“配慮事項”だけ。
ただ、このような医師からの診断書があっても、通っている私立中学では、おそらく特別な対応や支援はありません。
普通に漢字のテストは受けますし、間違っていたら点数を引かれます。
漢字や字が下手で怒られることはないので、もしかしたら、その辺の配慮はあるのかもしれません。
診断書がない同じような子と比較ができないため、詳しいところは分かりません。
その辺のことで、何か説明されたこともないので、おそらく特別な支援はないと思います。
でも、息子は幼い時から少しずつ間違うことへの耐性を付けて、受け入れられるようになりました。
皆と同じ条件の中で、一生懸命、頑張っています。
診断名は盲目的に使うものではない
私は、医師が上記のように記載してくれたことに、深く納得しています。
学校にとっては、「この子は自閉症です」と言われるより、
「こういう場面で困る可能性があるので、こう配慮してください」と言われた方が動きやすい。
そして、残念なことに、診断名への偏見が根強く残る現実もあります。
だからこそ、息子のように特性が薄れてきた場合は、あえて“使わない”という選択も正しいと思っています。
適応しているように見えるのは、環境が整っているから
しかし、おそらく今でも一般家庭に放り込まれたら不適応を起こすと思います。
息子を育ててきて、もう当たり前になってしまった私と夫の対応は、おそらく特別なものだと思います。
一つ例を取ると、中学一年生の頃の息子の成績は中の下でした。
けれど、塾には行かせませんでした。
おそらく、一般的な家庭だったら行かせるような成績でしたが……。
中学一年生の一年間は、中学に慣れることを最優先にしようと決めたからです。
担任が少し厳しい方で、苦言をいただきそうになりましたが、
「この一年は慣れることを最優先したいと考えています。環境の変化が大きく、それでも息子は頑張っています。親から見たら息子は100点満点です」と、親バカながらも担任に面談で伝えました。
でもこれは、ただの親バカ発言ではありません。
息子のような発達特性を持つ子にとって、「新しい環境に適応すること」こそが最大のチャレンジだからです。
このことを親が理解し、人前で子供を貶さないことは、子供との信頼関係を形成するうえで大事なことだと思っています。
自閉症スペクトラムの特性を持っている息子にとって、環境の変化は、大変なものです。
今までの経験から、入学一年目は荒れます。だから親も覚悟していました。
環境が整っていれば、二年目は絶好調になります。
まずは学校生活に慣れることを最優先にしました。
中学二年生になり、やはり、絶好調になりました。
自分から勉強の計画を立てて、自分で考えて勉強するようになりました。
成績は中間より上になりました。
次はもっと上を狙うんだと、やる気を出しています。
今も塾には行かせていません。
むしろ、中学二年生直前の春休みから、息子が通いたいと言った趣味の習い事を始めました。
北風と太陽のように、やれやれと言うよりも、やりたい環境を整えることが大事だと思っています。
やれやれと言ったこともありましたが、やらないんですよね(笑)
結局、環境が整わないと、やれないんです。
でもそれは、私たちだって同じですよね。
三者面談を嫌だと思わない息子
息子のクラスメイトたちは三者面談が嫌だと愚痴ってたらしく、息子はなぜそんなことを思うのか分からなかったらしいです。
息子は「嫌だ」という気持ちが全くなかったみたいで。
これは、たぶん息子が少数派だと思います。
多くの親御さんは、「担任に子供を褒めるようなことはしないからで、建前もあるだろうけど先生の前で子供を叱る親が多いと思うよ」と説明したら納得していました。
どうしても建前を言わなければならない時の事前準備
もし、どうしても相手との関係性が薄い場合や、強く言えない状況になることが分かっている場合は以下のように話しています。
【学校の面談バージョン】
①建前と本音の説明。
②「うちの愚息が」って子供を下げて言うのが日本の文化。本当はそう思っていなくても、そうするのが正解という雰囲気が今でもある。
③母ちゃんは全く思っていないけど「もーこの子ほんと勉強しなくて―、家で怒っておきますー!」って演技するかも。その方が早く話が終わるかもしれないから。
④でも実際は、家でそんなことは言わないし。あなたは100点満点。
このような話を息子に説明します。
まあ、今までも何度かこの説明はしていて、でも実際に人前で息子を下げていったことは数える程度……?
ママ友との間で、中学受験期に「うちの子、勉強しなくて」と言い合ったことはありますね。
でもこれも、こう言っておかないと、落ちた時に恥ずかしいから、勉強していてもみんな言うんだよと説明しました(笑)
建前と本音って、難しいんですよね。
診断が外れることはある。けれど、それをゴールにしないでほしい
この記事で伝えたいのは、「診断が外れた=勝ち」ではない、ということです。
診断名がなくなっても、そこで苦労は終わりじゃないです。
今でも、息子の中に発達特性はあります。
でも少しずつ成長しています。
目標は、自分で工夫して問題を解決できる力をつけること。
そして私は、こう思っています。
大切なのは「診断名」ではなく、「本人が生きやすい環境をつくること」。
それだけは、きっとこの先も変わらないでしょう。
今は親がしているこの環境整備を、いずれ息子自身で出来るようにこれからもアシストしていくつもりです。
もし今、お子さんに診断名がついたことで悩んでいる方がいたら、
「それは一つの情報であって、未来を縛るものじゃない」ということを、伝えたいです。
小さな積み重ねの先に、思いがけない景色が待っていることもあります。
そんな例が、ここにも一つあったのだと感じてもらえたら嬉しいです。
おわりに
我が家は、ものすごく恵まれていました。
療育にも早くつながれたし、医師や支援者にも恵まれていました。
何より、私は「放っておけば、将来どうなるか」を身をもって知っていたから、覚悟を持って育てることができました。(今回はこのことについては割愛します)
だからこれは、「たまたま奇跡が起きた話」ではなく、
支援と愛情と理解があれば、こんな未来もあるという一例として受け取ってもらえたら嬉しいです。

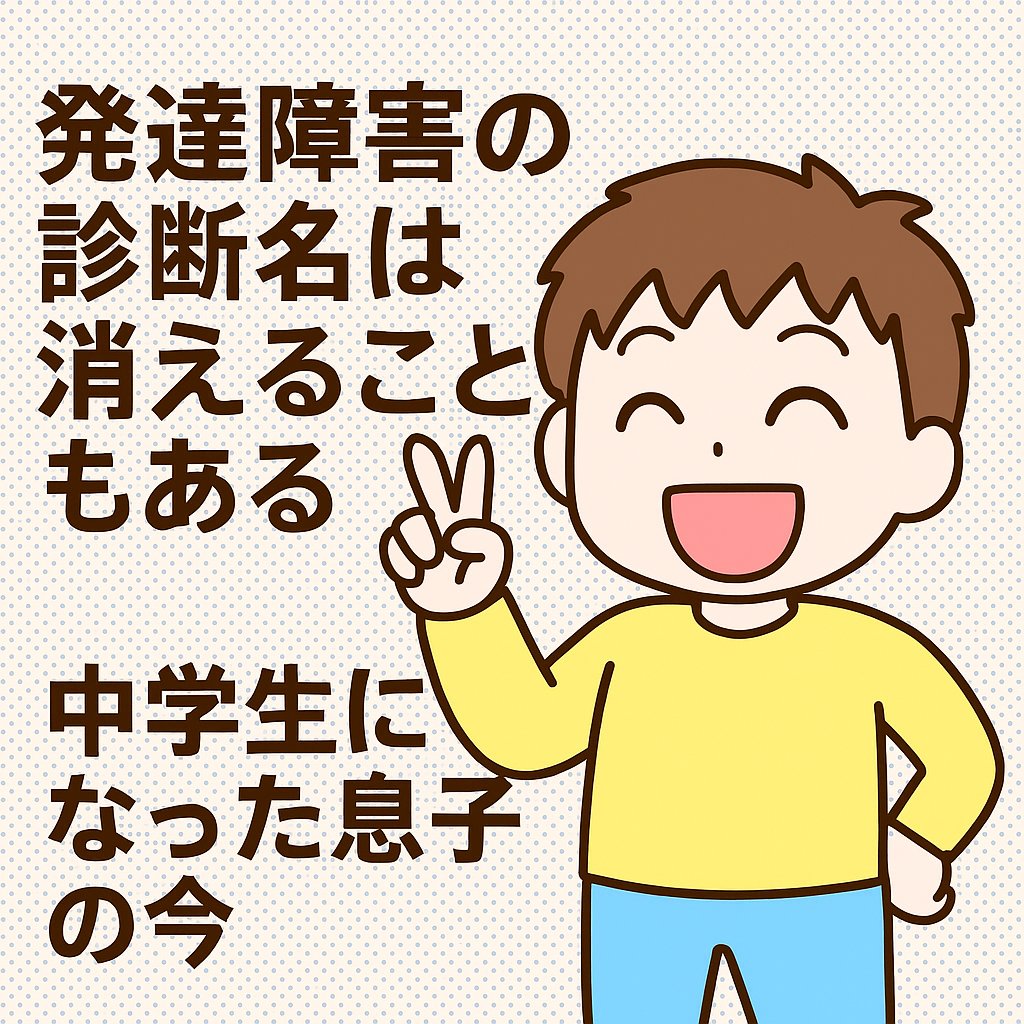


コメント